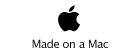久松Dr.のページ

第5回 日本人アテンディングがみるアメリカの医学生・研修医
13)日本と米国との医学生、研修医、指導医の違い
筆者は現在University of Pittsburgh Medical Center(ピッツバーグ大学メディカルセンター:以下UPMC) Shadyside病院内科研修プログラムの研修医として、米国臨床研修の真只中にある。母校の鹿児島大学病院で初期研修を1年間終え、沖縄県立中部病院にて初期と後期研修を4年間行った。鹿児島大学病院に戻ってからは、指導医として学生と研修医に4年間つき合い、渡米前の1年間は、札幌の手稲渓仁会病院にて、立ち上げて間もない研修プログラムの基礎固めに携った。大学・県立・民間の研修病院での教育・診療に関わってきた経歴であるため、そのような立場から今回のテーマへの発言を期待されている事を意識して以下に述べる。
1.医学生: 単刀直入に日本が米国に対して卒前臨床教育で勝っている点はあるのだろうか?そう思わせるぐらいに米国の医学生の能力は高い。米国では3年生から病棟に出てくるが、レジデントチームの1員として症例を持たされ、指導医・シニアレジデント・インターンからの徹底したチェックが入る。毎朝の回診で症例を提示し当日の方針を決めるが、これらは主にインターンの下での診療となり、全てにおいて医師のサインが必要になる。詳細な病歴聴取、理路整然とした症例提示(プレゼンテーション)の徹底的な訓練、研修医や指導医との活発なディスカッションを通して、基本的なマネージメント、オーダーの仕方等を学んでいく。
4年生はActing internとも呼ばれ診療への自由度は増し、より独立して診療にあたるようになる分責任は重くなる。立場はインターンに近く、シニアレジデントが直接の指導にあたることが多い。従って要求される内容も高い。受け持ち症例数が少ないというだけで、既に研修医並の診療が可能になってくる。
看護師を初めとしたパラメディカルの学生への態度も、日米では大きく異なる印象を受ける。担当医師のように対応してくれるし、またそのように行動することが要求されるので、学生としてはプロ予備軍として真剣に実習に望まざるを得ない雰囲気が、自然と作られている。
日本の医学生の大部分は、患者への関わりが制限されており、その分責任感も薄い。周囲が学生をお客さん扱いしている事も問題である。勿論学生個人の努力によっては、大きく関わることも可能だがそれには限界がある。私が大学に戻った際には、教授を初めとした診療科全体の理解の下に、学生をチームの一員として診療に積極的に参加させた。学生からの評判は総じて高かったが、これも一診療科だけの話であり、病院全体の体制というわけではなかった。全国にclinical clerkshipの概念が浸透している米国とは歴然とした差がある。またプレゼンテーション能力の弱さも目立つ。医師として求められる非常に重要なスキルであるにもかかわらず日本では認識が低く、プレゼンテーションの訓練を卒前教育のプログラムとして受けることは皆無ではなかろうか。充実が望まれる。これは卒後研修にも通じる点だが、米国ではレベルの底上げが強く、卒業までに最低限のレベルまでは持っていこうという明確な国家としての意志が感じられる。日本では学生間での差が大きすぎる。全ては卒業してからという医学部自体の意識が変わらなければ、この日米の差はずっと埋まらないであろう。
2.研修医:ここでは米国の内科研修医について、多少考え方に偏りがあるかもしれないが、日本と違う点に重点を置いて述べてみる。
米国の研修医は非常に忙しい。「日本の研修医も忙しいぞ!」という声が聞こえてきそうであり、実際私が研修した中部病院などは非常に忙しかった。しかし日本の場合には、特に大学病院等では研修医は忙しいといっても、内容が本来の診療以外の部分(研究の手伝い、学会発表準備、時には患者さんの搬送も研修医の担当だったりする、等々挙げればきりがない)に時間を取られ、だらだらと時間が過ぎていくことが多い。米国の場合には、早朝からとにかく診療に集中して1日が過ぎていくので、中身がとても濃いように感じる。UPMCの内科病棟では4日毎の当直で入院患者が計8名入ってくるので、患者をどんどん退院させなければならない。この患者は、どうしたら問題が解決して退院させられるのか、そればかりを考えている。カンファレンスの内容が充実している事は勿論だが、UPMCではポケットベルを入り口で秘書に預ける事になっており、緊急以外のコールには彼らが対応しメッセージを残しておいてくれる。よってこの時間帯は、そのカンファレンスに集中することができる。また正午に設定されているレクチャーには、必ず昼食が提供されるので、これが出席への動機付けともなっている。しかしカンファレンスの数が多くて、正直インターンには時に負担にもなる。忙しくて出席したくもない時もあるが、80%以上の出席が義務づけられており、出席率が悪いと当然ながら評価に響いてくる。よって早朝から(朝は5時起き)仕事を始め、カンファレンスに参加する時間を確保しておかなければならない。「忙し過ぎて」というのは理由にならず、time managementも大事な評価項目である。毎年半年過ぎた頃にプログラムディレクターとの面談があり、この出席率についても言及される。評価システムがしっかりとしており、しかも1年毎の契約なので次年度の契約書にサインするまでは不安である。設定された目標に3年間で到達させるために、とにかく濃密な内容となっている。
しかしながらマイナスの面も勿論ある。私の印象では研修医になると、忙しすぎて、身体所見をきちんと取らなくなるように思う。どの疾患でどのような異常所見が見られるかは知っていても、その所見をきちんと取れる医師が、内科の場合には果たして3年間で育っているのか甚だ疑問に思う。また入院期間短縮と訴訟対策もあり、最初からオーダーする検査も非常に多く、考えながら検査をオーダーしているのかと疑問に感じることも多々ある。きちんと身体所見が取れ、コストを踏まえた有効性を考慮して検査をオーダーするという、以前に伝えられていた米国臨床研修の特徴の一つは最早消えつつあるのではないだろうか。これは医療保険制度を含めた米国の医療制度の変化が大きく影響しているものと思う。更に研修医の医師患者関係も、日本と比べると稀薄ではないかと感じる。手技に関しては、3年間で要求される手技の内容と回数は決められているものの、実施する機会は日本に比べると断然少なく、皆上手くない。専門医制度が充実しており、研修終了後にそのような手技を実際に行う必要性が無くなってきているのも事実であるが、トレーニングを終え一般内科医を名乗るには寂しい気もする。日本の研修医の皆さんには、腹部エコーのトレーニングやCTを含めた読影能力、気管内挿管等の手技など幅広い技術の習得に努めてもらいたい。また前述した私が感じている現在の米国研修制度が抱えるマイナス面も反面教師として、是非日本の各研修プログラムで対策を講じてもらえたらと切に思う。
3.指導医: 日本の大学病院では、指導医には診療・教育・研究の業務が求められる事が多い。研究の成果が最も評価される現在の制度では、残念ながら教育は後回しになり、教育に時間を掛けられないと思っている医師が多いのが現実である。一方市中病院では研究の負担は少ないものの、指導医自身が外来や病棟での診療に割かれる時間が膨大となり、また給与の査定にも何ら影響しないので、やはり教育は二の次にならざるを得ない状況が作られている。個人の努力に依存するには限界があり、単なる自己満足では早晩燃え尽きてしまう。
これに対して米国では、内科系指導医にはTeaching attendingとして各レジデントのチームに参加する期間が数ヶ月義務づけられる。その月には自分の診療の時間が軽減される分、教育に重点を置かなければならない。Community-based hospitalでは開業医がTeaching attendingとして参加する事も珍しくない。私のいるShadyside病院はUPMC関連のcommunity hospitalであるので、teaching facultyと呼ばれる大学の一般内科所属の指導医が、その月のteaching attendingとして一つのチームを担当している一方で、開業医が別のチームを担当していたりする。米国では教えることで自分の知識も高められるという考え方が浸透している。また教育に従事する事は評価され、名誉へとつながっていく。大学の医師にとっては教育も契約に入っているので、給与の査定の対象にもなっているのだが、その他にも自己啓蒙と名誉というインセンティブが、米国の指導医には大きく働いているのである。日本でこのような意識が浸透していくには時間はかかるであろうが、新臨床研修制度が始まる今こそが、新しい考え方を受け入れていくに相応しい時であろう。
以上こちらに来てから感じていることを、日本での経験を踏まえながら述べさせて貰った。すぐに役立ちそうな目新しい事は伝えられなかった感も否めないが、日々研鑽を積まれている日本の研修医や指導医の方々が、少しでも各自の研修制度を改善するのに参考にして頂ければ幸いである。皆さん、一緒に頑張りましょう。
久松良和
University of Pittsburgh Medical Center Shadyside hospital内科研修医
久松先生の業績の一部を奥様より頂いたので、公開します。